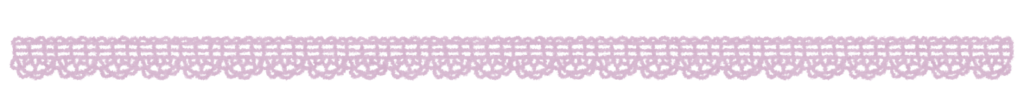こんにちわ。あやみんです。
よく心理やスピリチュアル界隈で感情を感じ切って手放す、
ということが言われていると思います。
大体は親のことだったりする場合が多いです。
かくいう私もそれ系に向き合ってきました。
カウンセリングを受けたり、
セミナー行ったり、
本を読んだり、体験された方のブログを読んだり。
親というか「自分」に向き合ってきました。
何故そうしたかったかのか。
幸せになりたい。
心穏やかに生きてみたい。
それもありましたが、
この訳のわからない苦しみからもう解放されたい。
が一番大きい理由だっと思います。
蓋をしてきたのは大体ネガティブな感情
心の底で押し込められてきた感情は
大体思い出したくないしんどい記憶。
子供だった私が、生き延びるために表に出さず隠してきたもの。
不機嫌な母親を怒らせないよう
仕事で疲れて休日には子供と話もしない父親の機嫌を損ねないよう
自分のネガティブは無かったことになってしまった。
そのまま大人になってしまった。
置き去りにしてしまった感情は
・悲しかった
・つらかった
・嫌だった
・話を聞いてほしかった
・寄り添って欲しかった
・理解して欲しかった
こんな感じです。
受け止めてもらえる場面や拠り所がなく、
積もり積もっていきました。
苦しみながら生きてきて、
生きづらさを自覚したのは40歳手前。
両親に愛されなかったという絶望
今まで色んな心理セラピーを受けてきました。
さっき書いたような感情を感じるワークもしました。
涙も出ました。
話して楽になりました。
けれども、何故そういう感情を感じるに至ったのか
そこまで考えたことはなかったのですが、
最近、社会心理学者の加藤諦三さんの本を読んで納得する部分がありました。
私は、経済的には何不自由なく育ててもらった。
しかし、心理的にはほとんど愛情をかけられずに大人になった。
ということです。
これは今まで思ったことがなく、
納得し難い、認め難い事柄でした。
何故なら一生懸命働いて育ててくれた両親を否定することになるから。
自分が家庭で両親に愛されなかったということを認めてしまうことになるから。
けれども本を読んで自分の中で確信しました。
私は心理的には愛されずに育ったんだと。
心理的な愛情をかけることが困難な両親だったのだと思います。
愛したい思いはあるけれども現実にはできなかったのかもしれません。
これは自分にとって悲しくて絶望を感じることでした。
でも深く納得した感はありました。
その後の自分の人生を見ていくと、
愛情に枯渇した私が依存にはまっていくことが容易に納得できました。
私には心の安全基地というものが自分の中にありませんでした。
心が育たないまま、身体は大人になってしまったのです。
両親もまた、心が育っていないまま大人になった人達だったのです。
底打ちしたら楽になった。
心が育っていなかった自分の半生を振り返ると
より自分の苦しみや失敗が理解できました。
悲しいけれどもそれが現実だったという
「真実」を受け入れると思ったより楽になりました。
楽になったというのは苦しまなくなったということです。
「諦め」にも似たような思いです。
子供の頃は、
どうしてこの人たち(両親)はそんなに子供好きじゃないのに
3人も子供を作ったのだろう、
どうして毎日不機嫌なんだろう、
どうして私にこんなに冷たいんだろう、
子供ながらに不思議に思っていたことがようやく理解できました。
ごく最近までは、私が良い子じゃないから親が不機嫌なのだと思っていましたが、
親が子を愛せない人達だったのだと理解することができました。
ようやく親孝行する気持ちに
人生の転機を経て自分に向き合い始める前から
両親とは距離を置いて接することが一番無難な生き方でした。
元々子供の頃から距離はあるので、今までと変わらずという感じ。
けれども色んなことが理解できてこれからは育ててもらった両親に
「大人の自分」ができることはしたいなあと肩の力を抜いて考えられるようになりました。
これから自分で育てていく
これからは「大人の私」を生きていく。
自分で自分のことを育てていきたいと思います。
話を聞いてくれる夫もいる、兄弟もいる、友人もいる。
何かあれば信頼のおけるカウンセラーさんもいる。
「大人の私」はボディセラピストとして
クライアントさんの癒しの手助けや心の余白作りに
貢献できる人間になっていきたいと思います。
補足
脱水症状で療養していた時に、加藤諦三さんの本を数冊読みました。
何を読んだのか、あえてタイトルは書かないことにしました。
何かを読んだら解決するという方法論ではなく
向き合い続ける、ということをブログに残したかったんです。
社会心理学者の加藤氏はたくさんの著書を出されているので、
ピンときたものを読まれることがいいと今時点で思っています。
今回はHPのリンクを貼ります。